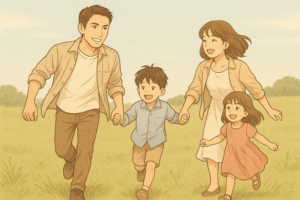七月七日の夜、天の川を挟んで輝く二つの星――牽牛星(けんぎゅうせい/アルタイル)と織女星(しょくじょせい/ベガ)が、年に一度だけ出会うという物語は、日本でも広く知られる七夕伝説の中心です。この伝承は中国の古代神話に由来し、日本には奈良時代に伝わったとされます。
中国ではこの夜、織女星にあやかり、特に女性たちが裁縫や機織りの上達を願う「乞巧奠(きこうでん)」という行事が行われていました。庭先や祭壇に針や糸、季節の野菜や果物を供え、技芸の向上や願い事の成就を祈るもので、これが日本に伝わって、平安時代には宮中の年中行事の一つとして定着していきました。
やがて時代が下るにつれて、この行事は武家や町人の間にも広まり、江戸時代になると庶民の間でも盛んに行われるようになります。その頃から現在のように、笹竹に願いごとを書いた「五色の短冊」を吊るす風習が広まりました。
この「五色」とは、青(緑)・赤・黄・白・黒(紫)で、陰陽五行説に基づいた五徳(仁・礼・信・義・智)を表すとされています。
また、もともと乞巧奠の供物であった五色の糸が、形を変えて短冊になったともいわれています。
七夕に使われる竹や笹は、古来より神聖な植物とされ、生命力が強く、真っ直ぐ天に向かって伸びることから、願いが天に届くと信じられてきました。風に揺れる笹の葉の音は、神を招く“神籬(ひもろぎ)”の役目を果たすともいわれています。地鎮祭の時などにも竹が使われますよね。竹も榊と並んで清浄な植物の一つとされているのです。
また、七夕竹は「七夕送り」として、お祭りが終わった後には川や海に流す習わしもありました。これは、短冊や飾りに託した願いや穢れを水に乗せて流すことで、心身を清め、新たな節目を迎えるという意味合いを持っていたのです。ちょうどお盆の直前にあたる七夕が、穢れを祓い、先祖の霊を迎える準備としての役割も果たしていたことがうかがえます。
こうして、七夕の竹飾りは単なる風習としてではなく、古代から続く願いと祓いの心を今に伝える大切な年中行事の一つとなっているのです。