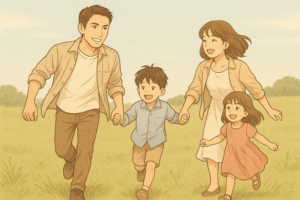私たちがいま「アクセサリー」として身につけている天然石の玉──それは、実は古代において神聖な意味をもつ祭祀の道具でした。美しさの裏に、祈りや信仰、そして人と神をつなぐための“言葉にならない対話”が込められていたのです。
古来より、玉(たま)は霊力を宿すとされ、神様との交信手段や、身を守る護符として大切に扱われてきました。日本においても縄文時代や弥生時代から玉の使用が見られ、勾玉(まがたま)をはじめとする多様な形状の玉が遺跡から出土しています。専門の職人や祭祀集団によって丁寧に作られ、代々受け継がれてきたのです。
形も様々で、代表的なものに勾玉、菅玉(すがたま)、丸玉、なつめ玉、切子玉などがありました。材質もまた多岐にわたり、真珠、翡翠、瑪瑙、琥珀、水晶、碧玉、滑石、ガラスなどが用いられています。これらの多くには穴が開けられ、糸を通して首にかけたり、腰に下げたりといった形で身につけられていたことがわかっています。
単なる装飾ではなく、「身につけることで邪気を祓い、心身を清める」「神の力を身近に呼び寄せる」といった呪術的・霊的な目的があったのです。とくに、勾玉は胎児の形に似ていることから“生命”そのものの象徴とされ、魂(たましい)をあらわす存在でもありました。その力強さから、やがて三種の神器のひとつとして、現代にも語り継がれています。
古代の人々が大切にしてきたこの“玉”の文化は、いま私たちが身につけているパワーストーンブレスレットにも、静かに、けれど確かに受け継がれているのかもしれません。
天然石で作るお守りブレスレット、…


縁起物とは – 天然石で作るお守りブレスレット、お守り数珠の販売・通販「コトホギ」
仏教では、この世のすべてのものは、互いに関わり合いながら成り立っていると考えられています。何かが存在するには、必ずそれを支える“縁(つながり)”があり、その仕組