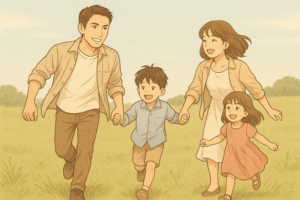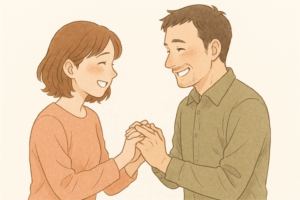宮中や神社では、毎年6月と12月の晦日(おおみそか)に、「大祓(おおはらえ)」という重要な神事が行われます。これは、日々の暮らしの中で知らず知らずのうちに積もった罪や穢れ(けがれ)を祓い清め、新たな気持ちで次の半年を迎えるための節目の儀式です。
6月に行われる方は「夏越(なごし)の祓」と呼ばれ、暑さとともに訪れる厄や疫病から身を守るという意味も込められています。

この夏越の祓の神事として、全国の神社で行われるのが「茅の輪(ちのわ)くぐり」です。境内の鳥居や拝殿の前に、茅(ちがや)という草で編まれた大きな輪「茅の輪」が設置されます。参拝者はこの輪をくぐることで、身についた穢れを祓い、無病息災や厄除けを祈願します。
茅の輪くぐりには一定の作法があり、まず左足から輪に入り、左回り・右回り・左回りと八の字を描くように3回くぐるのが一般的とされています。

また神社によっては、「人形(ひとがた)」と呼ばれる紙に自身の名前や年齢を書き、息を吹きかけて身代わりとし、それを川や海へ流す「形代(かたしろ)流し」が行われることもあります。これもまた、穢れを水に流して清めるという古くからの風習です。
この茅の輪くぐりの起源は、『蘇民将来(そみんしょうらい)』という伝承にあるとされています。古代の神・スサノオノミコトが旅の途中、貧しいながらも心からもてなしてくれた蘇民将来に、「茅の輪を腰につけておけば疫病から免れられる」と教えたという話です。この教えによって、蘇民将来の子孫は疫病から守られたとされ、茅の輪は災い除けの象徴として信仰されるようになりました。
現代においても、私たちは日々の忙しさの中で知らず知らずのうちに疲れや不安、穢れをためこんでいます。だからこそ、半年の節目に心身を整えるこの神事が、多くの人々にとって大切な“リセット”の時間として受け継がれているのでしょう。