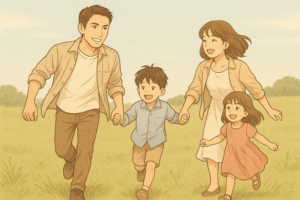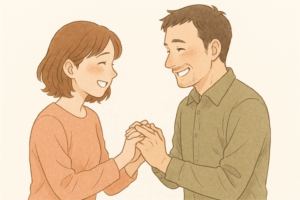蛇という生き物は、古来より人間にとって特別な存在でした。その細長く這う姿や、とぐろを巻く奇怪な形状から、不気味さや畏怖の対象とされる一方で、脱皮による再生や冬眠からの覚醒などの生態は、命の循環や再生の象徴とも重なり、神秘的な力を宿す存在として捉えられてきました。

特に毒を持つ蛇は、畏れられる一方で“無敵の強さ”を象徴する存在でもあり、生命力と死の境界を超える存在として、死と再生、破壊と創造の両面を併せ持つ霊獣とされてきました。実際、縄文時代の土器の中には、蛇を頭に戴く人面文様が刻まれたものも発見されており、人々が蛇を「命の根源」や「霊力の象徴」として深く信仰していたことがうかがえます。
このような蛇を神の使い、あるいは神そのものとする信仰が色濃く残っているのが、奈良県桜井市に鎮座する大神神社(おおみわじんじゃ)です。日本最古の神社のひとつとされるこの神社では、社殿を持たず、背後の三輪山(みわやま)そのものをご神体として仰いでおり、古代の自然信仰の姿を今に伝える極めて貴重な聖地です。
大神神社に祀られるのは大物主大神(おおものぬしのおおかみ)という神で、古事記や日本書紀の中で、しばしば蛇の姿と関係づけられて描かれています。特に有名なのが、「三輪山の神と女性の婚姻伝説」です。
あるとき、美しい女性・活玉依媛命(いくたまよりひめのみこと)が不思議な夢を見て身籠り、やがて男の子を産みました。その後、夜ごとに訪れる夫(=三輪の神)に「あなたの姿を見せてください」と願うと、ある朝、櫛箱(くしばこ)の中に小さな蛇の姿となって現れたのです。驚いた彼女が悲鳴を上げたことで、神は姿を消してしまいますが、この伝説は、神が蛇の姿をとって人のもとへ降りる存在であることを物語っています。
この伝承からも、大神神社では蛇は神そのものであり、またその神の使いとして白蛇信仰が受け継がれています。境内には実際に蛇が棲みつくとされる神木があり、白蛇を見ると縁起が良いとされることから、参拝者の間でも白蛇の目撃談は“吉兆”として語られています。
このように蛇は、単なる動物という枠を超えて、生命・再生・神秘・力・神性といった深い意味を宿し、太古の昔から私たちの祈りの対象であり続けてきました。