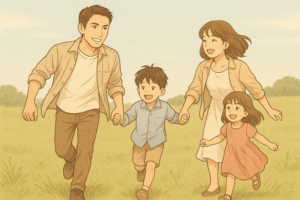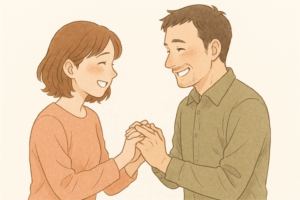『古事記』によれば、初代天皇である神武天皇(じんむてんのう)が東征の折、熊野の山中で道に迷い、進路に困っていた際に、天照大御神(アマテラスオオミカミ)が遣わしたとされるのが、「八咫烏(やたがらす)」です。八咫烏は三本足の神聖な烏で、神武天皇の軍勢を正しく導き、熊野から大和(現在の奈良県)への道を照らしたと伝えられています。

この神話により、八咫烏は神の使いとしての特別な存在となり、とりわけ熊野三山――すなわち熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社――においては、霊鳥として篤く信仰されています。熊野地方全体の精神的象徴として、八咫烏は広く知られ、現在でも熊野のシンボルとして、社紋や授与品、神社旗などにその姿が描かれています。
この八咫烏の信仰は、「牛王宝印(ごおうほういん)」と呼ばれる熊野三山の護符にも表れています。牛王宝印は、もとは仏教的な起源を持つ護符とされますが、熊野信仰のなかで独自の発展を遂げ、やがて神道とも融合して特別な霊力を持つ誓紙(せいし)へと変化しました。
その護符には、八咫烏を中心に、多くの烏が散りばめられた独特の意匠が施されており、古くはこの裏面に誓約文を書き、熊野の神々に誓いを立てるという風習がありました。この護符に記した誓いは極めて重く扱われ、誓いを破った者には厄災が降りかかると信じられ、「熊野の神の使いである烏が三羽死ぬ」「誓いを破る者は吐血して死ぬ」など、強力な霊的制裁を受けると語り継がれてきました。
この熊野誓紙(くまのせいし)は、庶民だけでなく武家社会にも広く受け入れられ、豊臣秀吉や徳川家康といった戦国大名たちも、家臣との主従関係を結ぶ際に、この牛王宝印を用いて誓約を交わした記録が残っています。単なる信仰の対象を超えて、神前の誓いを公的文書として機能させる力を持った存在であったのです。
今日でも熊野三山を参拝すると授与される牛王宝印は、厄除けや災難除け、誓願成就の護符として親しまれており、特に神聖な儀式や節目の祈願時に大切に用いられています。八咫烏の力を宿すその護符は、現代においても、心に強く響く「誓い」の象徴として生き続けているのです。